こんにちは、森です。
今、僕は長女のソフィアと
日本に滞在しています。
彼女を日本の幼稚園に通わせるために
数ヶ月だけ2人で帰国中です。
一方で、妻と次女のアマヤは
ロシアに残っています。
というのも、
ちょうど新しく購入した
マンションの引き渡しがあり
内装工事の手配や現場監督をするために、
妻が職人さんたちとロシアカザン街に
滞在しているんです。
アマヤはというと
田舎に住むおばあちゃんの家に
預けられていて
日中はそこの保育園に通っています。
朝8時から夕方5時まで
預かってくれる保育園です。
しかも、朝食と昼食、軽い夕食も出る。
「え、住民票とか? 書類提出とか?
お母さんの就労証明書は?」
そんなこと、聞かれません。
ロシアの保育園は、とにかくシンプル。
住民登録があれば預けられる。
親が働いていようがいまいが関係ない。
それが当たり前。
なんなら、
「お母さんが大変だからこそ預けるんでしょ」
という雰囲気さえあります。
もちろん強制では無いので、
「私は家で子供を育てたいです!」
って人はそれはそれで全然OKですし
基本的に保育園へ通わせて
午前中だけって人も多いです。
そんな圧倒的な“受け皿の広さ”に救われるロシアの子育て環境
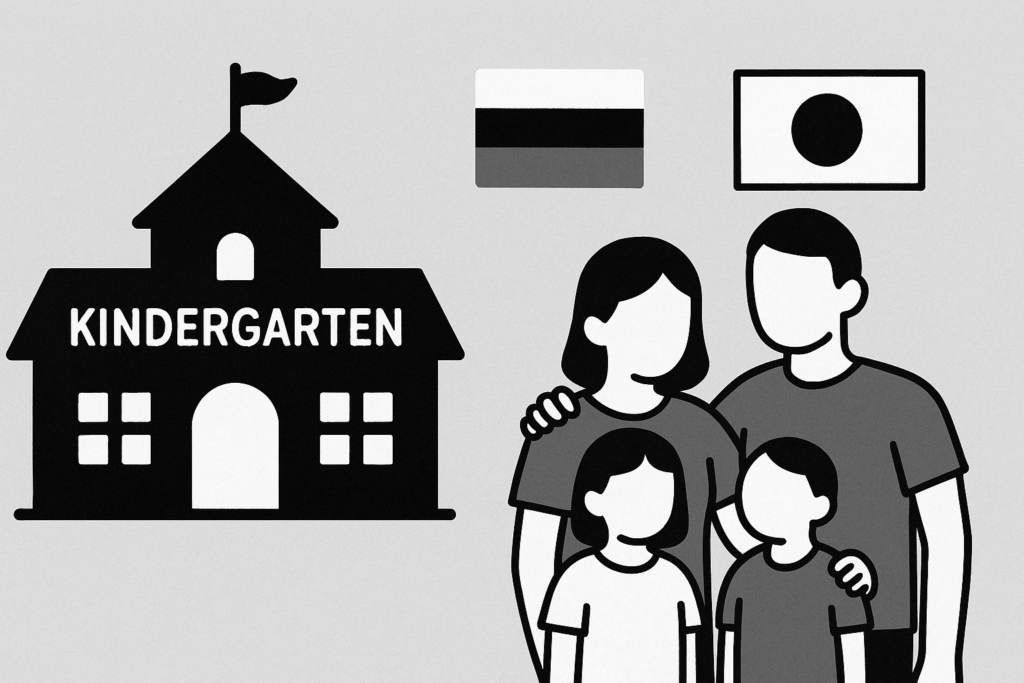
保育園の数も圧倒的です。
もちろん、
街中の人気エリアでは待ちもありますが
少し車を走らせれば
すぐに預け先が見つかります。
「困ってるなら、ここ使っていいよ」
とごり押しで通してくれることも
珍しくありません。
しかも、2歳から通える。
オムツが取れていなくても問題ない。
むしろ、園でオムツトレーニング
までしてくれます。
日本だと、
「家が汚れるから」
「床が濡れるから」
と、家でのトレーニングが
なかなか進まないケースも多いです。
でもロシアでは、
「漏らしてもいいよ、気にしないで」
と受け止めてくれる人がほとんどです。
実際、子ども立ちがまだ小さい頃
いろんな人の家に遊びに行きましたが、
「オムツしてたら外していいよ
漏らしても全然いいから」
って言われるのが本当に普通でした。
おしっこをして濡れて、
「パンツが濡れて気持ち悪い」
っていう体験こそが
子どもにとっての学びだという考え方が
根付いてるんですよね。
だからロシアでは
ほとんどの子どもが2歳でオムツが外れます。
親が熱心にやってるというよりは
保育園の中で自然に進む感じです。
一方、日本の“保育ハードル”に感じる大変さ
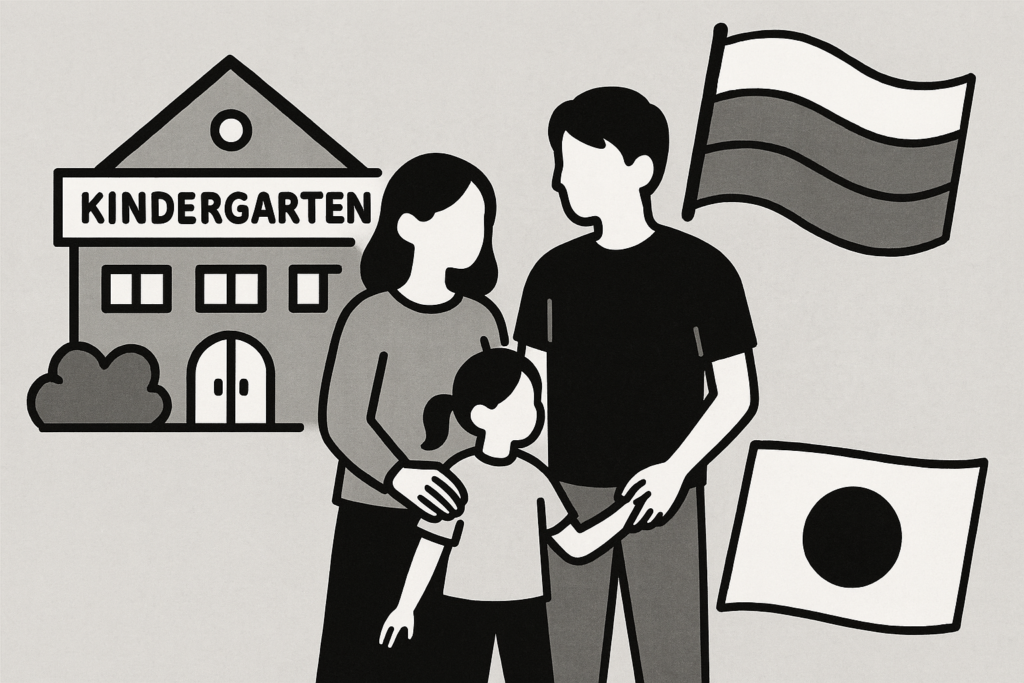
この差を、日本に来てから
改めて痛感しています。
日本では、
祖父母と同居していたら
「面倒見られるでしょ」
ということで保育園は門前払い。
幼稚園だとしても、
母親が専業主婦なら
「2時までしか預かれません」
なんてことも。
そして必ず問われるのが、
「お父さんの仕事」
「お母さんの仕事」――。
家庭の状況を細かくチェックされた上で
「保育に欠ける」
と判断されないと預けられない。
でも、
今の時代って共働きしないと
生活水準を維持できない家庭が
ほとんどなんですよね。
「子どもを預けられない=働けない=生活が苦しくなる」
という矛盾が起きてしまう。
そりゃあ、子どもを産むハードルも
高くなるわけです。
「この国で本当に育てていけるのか…」
って、不安になるのも無理はない。
子育てを「個人の責任」にしない社会に
ロシアでの子育てを通して感じるのは
制度やインフラだけじゃなく、
「社会全体の空気」
が子育てを支えているということ。
保育園や学校は、あらかじめ
“十分な数”を先に作っておく。
子どもが増えてから慌てて
対応するのではなく、
「増えても大丈夫ですよ」
と、先に器を整えておく。
これは本当に大きいです。
一方で、日本ではどうでしょうか。
「待機児童ゼロを目指します」
「子どもを産み育てやすい社会に」
そんなことが長年言われ続けていますが
結局のところ、保育園の数は足りていない。
共働きをしなければ
暮らしていけないような経済状況を
作ってしまったのも
景気対策が不十分だった政府の責任です。
それなのに、
「育児も仕事も全部家庭でなんとかしてね」
というのはあまりにも
無理がありますよね。
僕は、
誰か個人を責めたいわけじゃありません。
子どもを産みたくても産めない状況に
追い込まれている人たちのせいじゃない。
それはもう、社会の仕組み
そして優先順位の問題です。
ロシアでは
先に保育園をどんどん建てて、
「だから、安心して子どもを
産んでくださいね」
という姿勢が伝わってきます。
日本は逆。
人があふれてから、
「じゃあ保育園を作らなきゃ」
という“後手”の発想なんですよね。
子どもがいないから保育園が作れない
ではなく、
保育園があるから子どもを産もうと思える――。
そんな循環が必要なんじゃないかと思うんです。
ロシアでは“家族が当たり前に助ける文化”がある
ロシアにいる妻の家族――
つまり義理のお兄さん夫婦にも
子どもがいます。
その姪っ子と甥っ子は夏休みの3ヶ月間
丸々おばあちゃんの家に“全泊”してます。
お兄さん夫婦は仕事があるから
平日は完全に預けっきり。
週末だけおばあちゃん家に顔を出して
様子を見に行く感じです。
おばあちゃんも、
「子どもたちが元気に過ごしてるなら
それでいいのよ」
というスタンス。
一方で、今僕が日本の実家にいて
ソフィアを1週間預けようと思ったら……
正直、気が引けます。
預けたら面倒見てくれるとは思う。
でも、なんとなく
「ごめんね」「申し訳ない」
が先に立ってしまう。
でも僕は、将来ソフィアたちが大人になって
彼女たちの子どもを育てる時、
「日本語覚えさせたいから
3ヶ月だけ預かってくれる?」
って言われたら
即答で、
「いいよ」
って言える存在でいたいと思ってます。
もちろん、
本人たちが嫌がったら無理はさせませんが
少しずつ慣れていけばいい。
僕の子どもたちや孫が困った時に
気持ちよく「頼れる場所」でいたいなって。
おわりに:僕たちは、どう生きたいか
僕は、日本が悪いとかロシアが完璧とか
そんなつもりはありません。
ただ、両方の国で子育てを経験してみて
はっきり言えるのは、
「ロシアの方が、子どもを産んだ後の器が
しっかりしている」
ということ。
それだけで子どもを産むハードルが
下がるんです。
そして、家族のあり方も含めて
僕自身がどんな人でありたいか――
それは、
“孫に頼られたらいつでも
受け入れられる器を持った存在”
でいたいということ。
保育制度がどうであれ
社会がどうであれ、
まずは僕自身が、家族にとっての
“安心できる居場所”になりたいな
そう思っています。
少子化の原因って
単にお金や制度だけじゃない。
「この国で安心して子どもを育てられるか?」
という、心理的な安心感も
含まれていると思うから。








